2025.01.25
- 活動報告
【南中野包括】ケース検討で看取りの意思決定支援を考える
当センターでは、定期的に「ケース検討」の時間をつくっています。
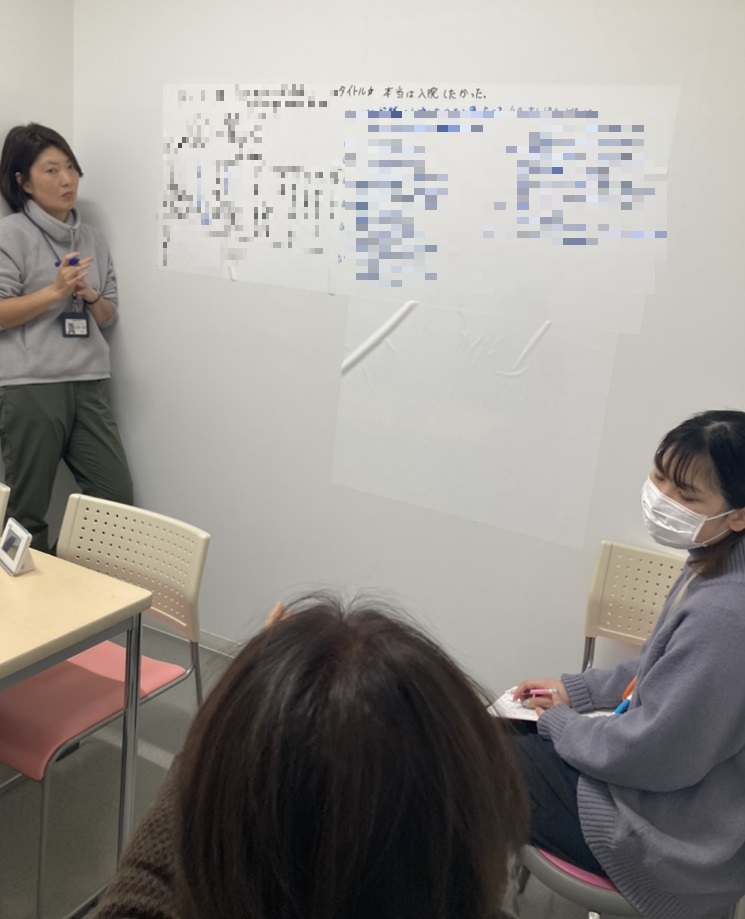
支援で悩んでいる、他に方法がないか不安、貴重な経験をしたので皆で共有したい、などなど、その都度ケースを1件挙げて、1時間かけて皆で考え合います。
当センターには多職種(主任ケアマネ・ケアマネ・保健師・看護師・社会福祉士)がいるので、それぞれの視点からの疑問や意見をたくさん出してもらいます。
ケース検討を開始してしばらく経ちましたので、ここでケース検討の意義や進め方の「まとめ」も行ないました。
一番大事にすることは、「気兼ねなく発言ができる」ことです。職種や経験や年齢や職位などは置いておいて、このケースについて自由に発言ができることを大事にすることを改めて確認しました。
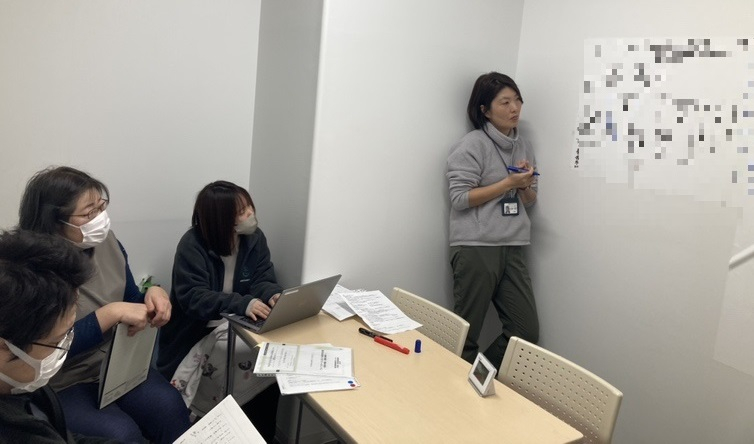
今回のケースは、短期間でお看取りに至ったケースで、ご本人の意向が最後まで把握が難しく、担当者から皆で振り返りをしたい、と挙げられたケースでした。
癌は終末期であっても、相談に至る段階ではまだ自覚症状が乏しかったり、身体も動くので、ご本人もご家族もなかなか実感できないことも多いです。
最近は身寄りがない、あっても頼りたくない(断絶している)方も多く、緊急連絡先や契約・支払いを誰がするか、という問題も出てきます。
今回のケースでは、ご本人はいわゆる認知症ではないけれど、病状や治療についての説明の理解や判断が難しく、本人の明確な意思のもとで進めていくことに関係者は苦慮しました。
頼れる身内もいないため、本来なら成年後見制度の利用も検討なのですが、数か月も時間がかかるため、間に合いません。
病院ソーシャルワーカーや包括職員が説明・説得を重ね、なんとかホームロイヤー(※)についてもらうことができました。
※ホームロイヤーとは
(日弁連HPより:認知症などで判断能力が低下したときに、契約者と一緒にもしくは契約者に代わって、財産管理や生活・介護・医療サービス等を受けられるようサポートします。)
退院後についた在宅医の先生からの予後や治療の説明をもとに、ホームロイヤーの弁護士が本人の意思・意向が叶えられるよう手続きを行う、という体制なのですが、これもまた本人の意向の表出が難しいため簡単には進みませんでした。
ケアマネジャーは、療養環境や医療介護の日々の体制の調整に追われ、包括職員はカンファレンスなど全体の調整を行いながら、ご本人とのやりとりの中で意思を汲み取ろうと努力しました。
だんだんとご本人が話をしてくれる中で、これまでの生き方、そこから見える考え方を汲み取り、関係者と共有しながら、ご本人はきっとこうしたい、ということなのではないかと。
最期は自宅か、入院か、ぎりぎりまで本人を囲んで決まりませんでしたが、細かな情報共有を重ねながらご自宅で息を引き取られました。
今回ケース検討で、時系列に、また本人に関する情報から人となりを想像しながら、「意思決定支援」のためには、どこの段階でどのようなアプローチができたか、について考え合ったことは、大変貴重な時間となりました。
長くなりましたが、今回の方からも大事なことを教わりました。こうして一つ一つの支援を大事にして、職員が育ち、チームとして支援力が高まるよう今後も取り組んでいきたいと思っています。


