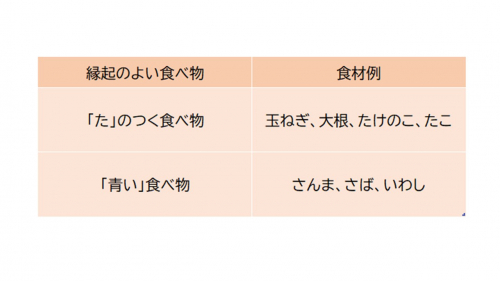2025.10.19
- お知らせ
【日常に役立つ・頭の体操】「秋の七草」の名前、いくつ言えますか?
日に日に涼しくなり、秋の深まりを感じますね。「秋といえば〇〇」と、色々なものが思い浮かびますが、日本の秋の風情を語る上で欠かせないのが「秋の七草」です。
春の七草(セリ、ナズナ…)は「七草粥にして食べる」のが目的ですが、秋の七草は**「眺めて楽しむ」**のが目的です。
さて、ここで皆さんに頭の体操です。秋の七草、全部で7つの名前をいくつ思い出せるでしょうか?
秋の七草を思い出してみましょう!全部言えたら素晴らしい! ひとつでも思い出せたら拍手です!
1 秋のお彼岸に食べる「おはぎ」の由来になったとも言われる、小さな紫や赤の花が垂れ下がる草木。
2 秋のお月見に欠かせない、動物のしっぽのような穂を持つ植物。(ススキのこと)
3 大きな葉を持つつる性の植物。根から葛粉(くずもち、葛湯)が作られます。
4 「大和撫子」の名の由来となった、繊細で美しい花。
5 黄色い小さな花をたくさん咲かせる草。
6 淡い紫色の小さな花を房状につける、上品な草花。
7 紫色の星のような形をした美しい花。
7つの名前を覚えるのはなかなか大変ですね。そんな時は、昔から伝わる「語呂合わせ」が、脳の活性化に役立ちます!
一番有名で覚えやすいのは、このフレーズです。
「お・す・き・な・ふ・く・は?」
このフレーズを何度か声に出して言ってみましょう。歌うように口ずさむと、さらに頭に残りますよ!