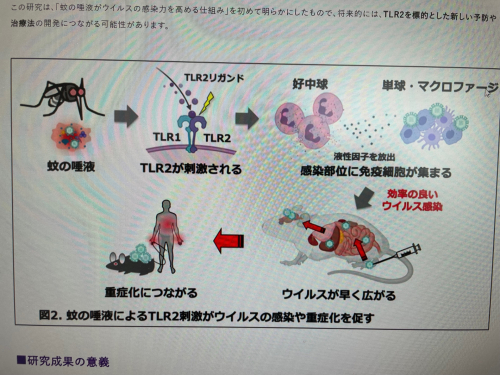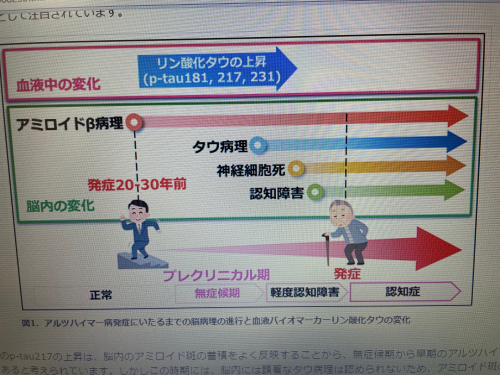2025.09.03
- ニュース
「リキッドバイオプシー」って何?
「リキッドバイオプシー」という言葉を聞いたことがありますか?これは、血液や尿、脳脊髄液などの体液を採取し、そこに含まれる遺伝子や酵素などを分析して疾患診断を行う技術のことです。生体組織を採取する方法と比べて体への負担を抑えられるといわれています。その「リキッドバイオプシー」において、「診断指標となるバイオマーカー酵素を、高感度、かつ高い識別能で複数種を同時に定量することが可能となった」と発表したのは、理化学研究所(理研)開拓研究所および東京都健康長寿医療センターの共同研究グループです。脳脊髄液などの液性検体に含まれる複数種のバイオマーカー酵素を1分子レベルで高感度に識別し、個数を定量可能な「1分子デジタルSERS計数法」の開発に成功した、と述べています。現在、リキッドバイオプシーは、がんをはじめとする基礎疾患から感染症に至るまで、医療現場での応用が進んでいるそうです。中でも酵素は、疾患の進行に応じて液性検体中の濃度が変動するため、古くから疾患診断の指標(バイオマーカー)として用いられてきましたが、従来の検査法では、異なる酵素種を識別すること(高い識別能)や、複数種類の酵素を同時に定量すること(多項目測定)には制約があったといいます。しかし、本研究で開発された「1分子デジタルSERS計数法は、液性検体に含まれる微量な酵素を高感度かつ高速に定量可能な革新的技術であり、リキッドバイオプシーの高度化に資する新たな計測基盤としての有用性が示された」ということです。本研究グループは、今後「認知症をはじめとする神経変性疾患に加え、がん、代謝疾患、炎症性疾患など、さまざまな病態に関与するバイオマーカー酵素の高精度解析が可能となるなど、本技術の汎用性はさらに広がることが見込まれるとともに、次世代医療における分子診断装置の中核技術としての発展が期待される」と結んでいます。
バイオマーカーの1分子デジタルSERS計数法を開発 | 理化学研究所
画像はプレスリリースから引用させていただきました。
SM