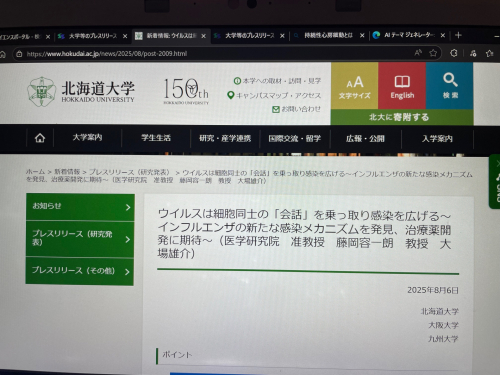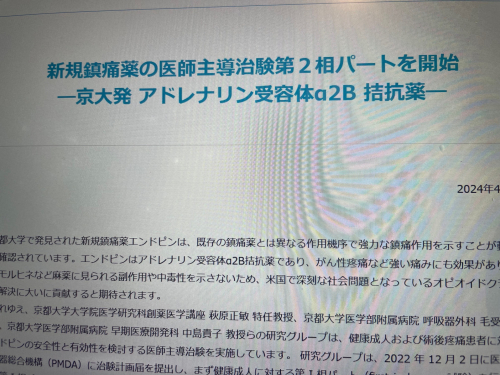2025.08.13
- ニュース
持続性心房細動アブレーション後の新たな指標
「持続性心房細動に対するカテーテルアブレーション治療後、左心房の最終的な大きさが大きいほど、その後の重篤な病気の発生率が有意に増加することを発見した」と発表したのは、山口大学大学院医学系研究科 器官病態内科学講座の研究グループです。つまり、持続性心房細動アブレーション後の長期予後予測における新たな指標として、左心房が「どれだけ縮小したか」より「どれくらいの大きさになったか」が重要であると述べています。具体的には、持続性心房細動に対する初回カテーテルアブレーションを受けた患者365名を対象に行った調査を解析し、上述の結果に至ったというわけです。本研究グループは、「心房細動のアブレーションを受ける症例が対象となり、左心房の容積だけでなく、その機能や、心房細動の重症度や併存疾患の状態など、包括的な情報を収集し、その中に心房心筋症が潜在する症例を早期に診断するための予測方法の確立を目指したい」と結んでいます。因みに持続性心房細動とは、「心房が持続的に小刻みで震えている状態のことをいい、この状態が続くと心臓から血液を送りだす力が弱くなり、結果として血栓を作る原因になる症状です。
(カテーテルアブレーションとは、不整脈の治療の一つで、不整脈の原因となる箇所にカテーテルを入れて血流を改善する手術のことです)
持続性心房細動アブレーション後の長期予後予測における新たな指標を発見 ―左心房が「どれだけ縮小したか」より「どれくらいの大きさになったか」が重要であることを解明― | 国立大学法人 山口大学
画像はプレスリリースから引用させて頂きました。
SM