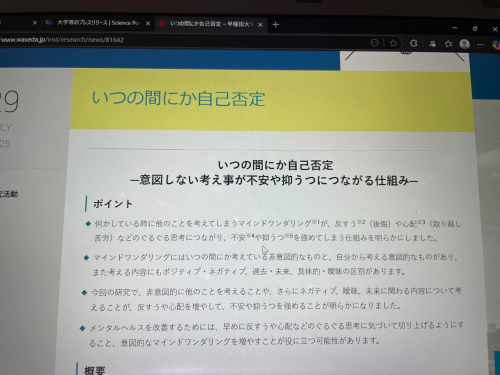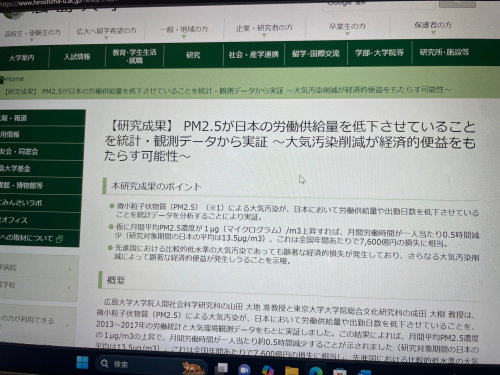2025.08.01
- ニュース
血管は管をつくりながら枝を伸ばす?
宮崎大学医学部機能制御学講座血管動態生化学らの研究グループは、「血管を新しくつくる血管新生において、血管基底膜による血管周囲の硬さと、血流によってもたらされる血管内圧との力バランスが、管腔構造をつくりながら血管の枝を伸長するために重要であることを発見した」と発表しました。具体的には、どのような研究だったのでしょうか。当プレスリリースによると、血管が新しく作られる場合では、管腔(血液が通るための管状の構造)がつくられながら血管の枝が伸びるそうです。ただ、「血管の伸び」と「管腔をつくる」ことは、異なる2つの現象だとか。実際、どのように2つが関係して血管新生が制御されているのかは不明だったそうです。そこで、本研究では、「血管新生と、血流によってもたらされる血管内圧の両方を、微小流体 デバイス上で再現する試験管内モデルのライブイメージング解析を独自に開発」したとか。そして、この解析法を用いて、管腔形成後、血管内圧の上昇に伴って血管の拡張が起きると、血管内皮細胞の移動が減速・停止し、血管の伸びが遅れる現象を発見した」というのです。 本研究グループは、血管網が適切に作られるメカニズムを明らかにするため、血管新生と呼ばれる現象に着目して研究を行ったそうです。因みに、血管新生とは、すでに存在する血管から新たな血管が出芽し、それが伸びて新しい血管網がつくられる現象のこと。生命が誕生、成長して体の組織や臓器がつくられる時はもちろん、我々の体がつくられた後にも生じ、例えば、創傷後の組織修復とともに、壊された血管ネットワーク自体も血管新生により修復されるそうです。本研究グループは、「臓器の発生・発達における力学的な環境の重要性を示唆し、がんなどの不適切な血管新生を背景とする疾患において、血管新生を標的とした新たな治療戦略の開発に貢献するものと期待される」と結んでいます。
因みに本研究は、著者らが熊本大学国際先端医学研究機構(IRCMS)所属時に開始し、宮崎大学への研究室移転後継続して行ったものだそうです。
画像はプレスリリースから引用させて頂きました。
SM